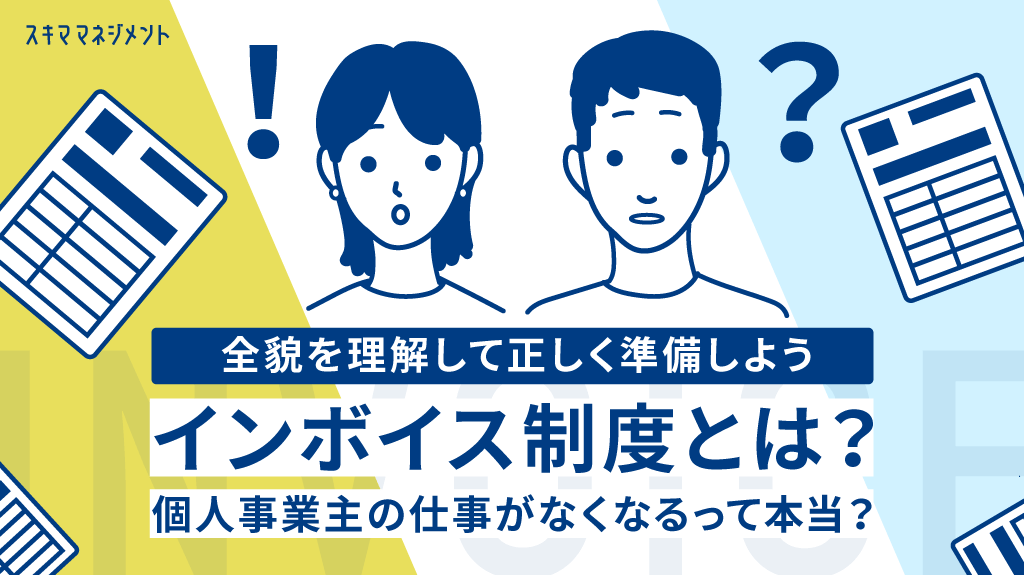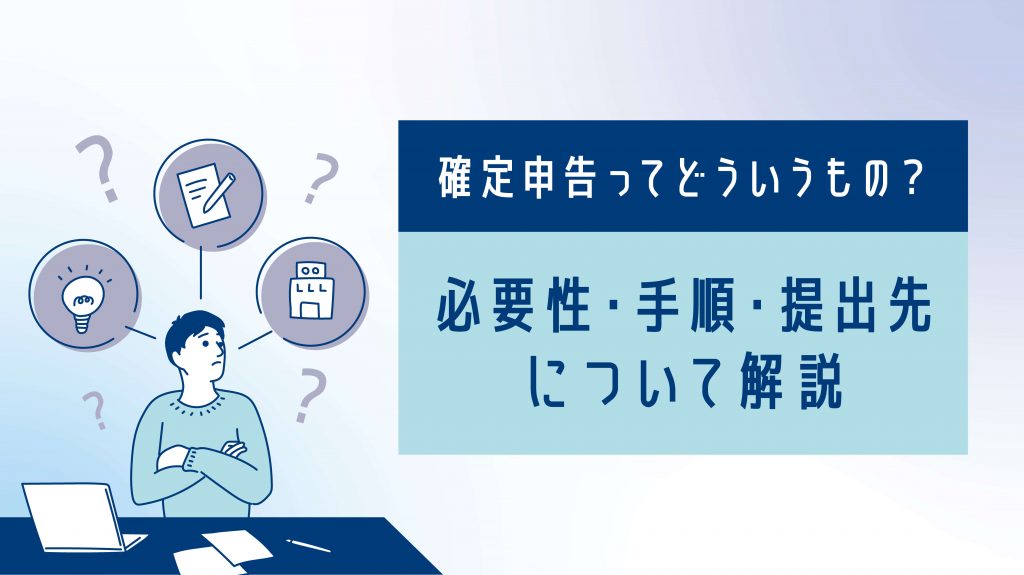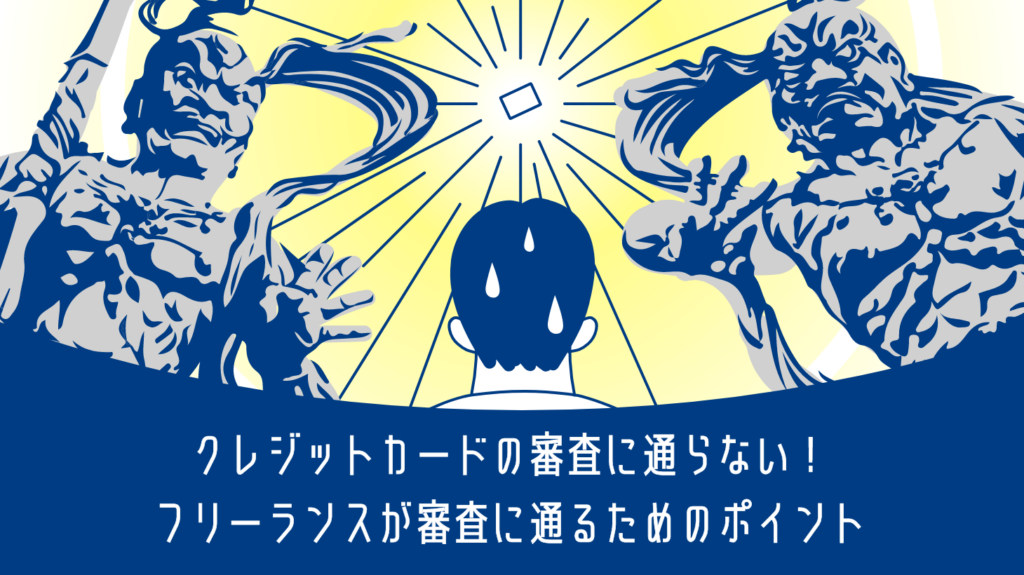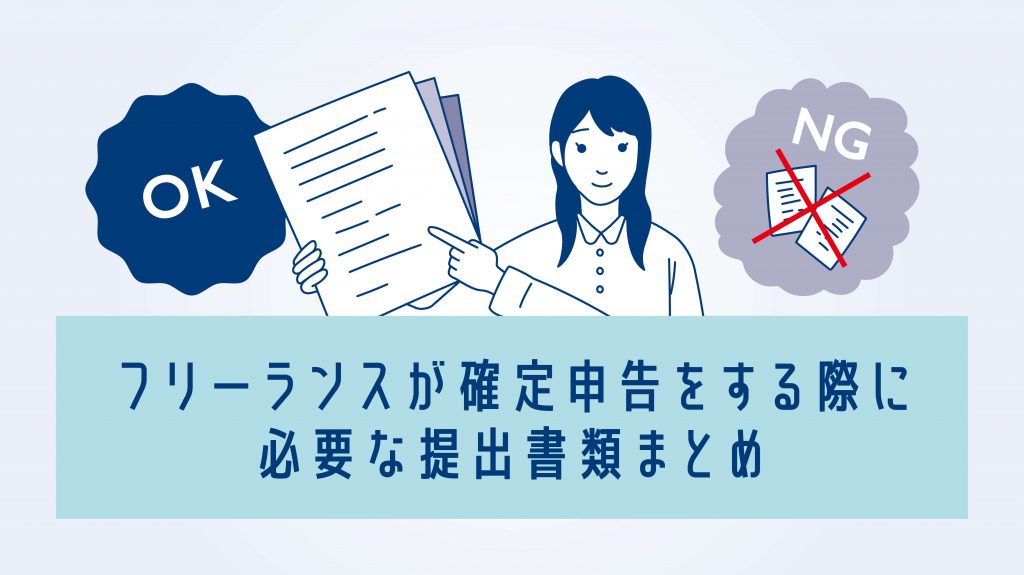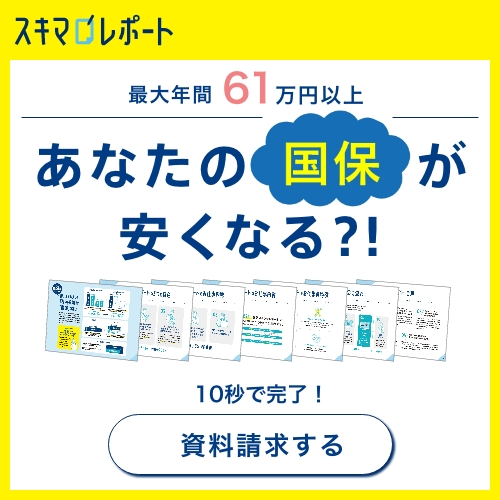フリーランスなら知っておきたい節税のポイントをまとめて解説
2021.09.16
スキママネジメント運営部
・フリーランスが払う税金はなにがあるか知りたい
・節税のポイントと考え方を知りたい
会社員時代はそれほど気にならなかったのに、フリーランスになってから急に税金が気になり始める方は多いのではないでしょうか。また、フリーランスとして収入が増えるにつれて、「少しでも税金を抑えたい」、「せっかく稼いだのに税金で持っていかれるのは嫌だ」と思い始める方もいるでしょう。
税金を抑えたいときに覚えておきたいのが、節税対策です。本記事では、フリーランスなら知っておきたい節税のポイントを解説します。
税額の決まり方とは?
フリーランスが負担する税金には、所得税や住民税などがあります。
これらの税額は、次のように計算します。
- 税額 = 所得( 収入 - 必要経費 - 所得控除 ) × 税率 - 税額控除
「収入」から「必要経費」と「所得控除」を差し引くと「所得」が算出されます。
そして「所得」から「税率」を掛けて「税額控除」で引くと税額が算出されます。
つまり、必要経費や所得控除、税額控除が大きくなるほどに納めるべき税額が低くなるのです。
税率は、所得税や住民税など税金の種類によって異なります。
フリーランスが支払う税金 4種類
フリーランスが支払う税金にも様々なものがあり、個々の税金によって税率の決められ方も違います。この章ではフリーランスが支払う税金の種類を紹介します。
所得税
所得税は個人の所得に対して課せられる税金です。
所得税の税額は以下の表のように所得額に応じて、税率が上がる「超過累進課税」方式によって決められます。

出典:No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
例えば所得が3,000,000円だとした場合は、表を見ると3,000,000円に該当するのが税率10%なので3,000,000円全てに税率10%が掛けられると思いがちですが、1,949,000円までの金額に対しては税率5%が掛けられます。
そのため税額を計算する計算式は以下のようになります。
- 1,94万9,000円 × 5%(税率) = 97,450円
- 1,05万1,000円(300万円 - 1,94万9,000円) × 10%(税率) - 97,500円(控除額) = 7,600円
このように5%と10%の税率に掛けられる分を個別に計算して、双方を合算した額が所得税額になります。この場合は105,050円(97,450円 + 7,600円)が所得税額となります。
住民税
住民税は、自分が住んでいる都道府県や市町村に対して納める税金です。所得税とは違い所得の増減で税率が変化することはありません。
住民税の税率は大体10%になります。
住民税の税額は「所得割」と「均等割」の2つを合算した額で決まります
- 所得割とは、毎年1月から12月までの所得に税率を掛けて計算する税
- 均等割とは、所得の額関係なしに定額で課税される税
所得割の額は「都道府県民税」と「市民町村民税」の2つを合算した額です。
所得割の税率と均等割の税額は以下が基本です。
| 都道府県税 | 市区町村民税 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 所得割 | 4% | 6% | 10% |
| 均等割 | 1,500円 | 3,500円 | 5,000円 |
出典:総務省「個人住民税の概要」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000696141.pdf
例えば所得が300万円だとした場合は、所得割の税額は30万(120,000+180,000)です。
以下がその計算の流れです。
- 都道府県税:120,000円 (3,000,000円 × 4%)
- 市区町村税:180,000円 (3,000,000円 × 6%)
この都道府県税と市区町村税を足した額が所得割の額です。
- 所得割:300,000円 (120,000 + 180,000)
そして所得割と均等割を合算した額が住民税の額となります。
- 300,000円(所得割) + 5,000円(均等割) = 305,000円
よってこの場合の住民税額は、305,000円となります
以上が住民税の計算の基本ですが、自治体によって税率が若干異なる場合もあるので、詳しくは住んでいる自治体のホームページで確認してみましょう。
個人事業税
個人事業税は事業で得た所得が290万円を超えると課せられる税金です。
ただし、全ての業種に課せられるわけではありません。
税率は「第一種事業(5%)」「第二種事業(4%)」「第三種事業(3~5%)」です。
例えば、デザイナーの仕事をしている人なら、第三種事業のデザイン業(5%)に該当します。
一方ライターの仕事をしている人なら、執筆業はどれにも該当しないので税率がかかりません。
どの業種に個人事業税がかかるのか?に関しては、以下の国税庁のHPを参照してみると確認できます。
参考:個人事業税 | 税金の種類 | 東京都主税局
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html#gaiyo_04
消費税
消費税とは、商品やサービスなどを購入した際に課せられる税金です。
フリーランスの売上にも消費税がかかりますが、2年前の売上高が1,000万円以下の場合は「免税事業者」となり、課税の義務がありません。
節税するには経費と控除を見直そう
売上から経費や控除を差し引いて残った所得に課税されるため、経費と控除を増やすことが節税の基本となります。増やすといっても、経費に計上できるものは決まっているため、「経費にできるものは必ず経費に計上して余計な税金を払わないようにする」というのが正しいです。
ここでは、フリーランスが計上できる経費と控除について解説します。
経費で節税する
経費とは、事業で収入を得るためにかかった支出のことです。
ライターに例えると、取材先に行く際にかかった交通費や、情報収集のために購入した書籍の代金などが該当します。
経費を多く計上すればするほどに節税額が大きくなるので、事業で収入を得るためにかかった支出は忘れずに帳簿などに記録しておきましょう。
会計ソフトや事業用のクレジットカードなどを活用すると、経費の管理がしやすくなるのでおすすめです。
経費にできる支出は?
フリーランスが経費にできる支出は次のとおりです。
| 交際費 | 営業目的での接待の飲食代 |
|---|---|
| 取材費 | 取材でかかった電車、バス、タクシー、宿泊代など |
| 修繕費 | パソコンやカメラの修理代など |
| 広告宣伝費 | Webサイトの制作費や広告掲載料など |
| 新聞図書費 | 書籍、電子書籍、新聞、雑誌など |
| 会議費 | 打ち合わせの飲食代など |
| 外注費 | 外部への外注費用など |
| 通信費 | インターネット利用料、電話代、サーバー代、ドメイン代など |
| 水道光熱費 | 電気代、ガス代、水道代など |
| 研修費 | セミナー参加費用など |
| 租税公課 | 一部の税金(事業に関わる税金)、収入印紙代など |
在宅で仕事をしている人は、家賃や水道光熱費、インターネット利用料などが生活用と事業用で混在します。この場合、事業にかかった費用分だけ経費に計上できます。この方法を「家事按分」といいます。
例えば、部屋の半分を事業に使用している場合は、家賃の5割を経費に計上できます。
また税金に関しても、事業で収入を得るためにかかった税金ならば経費に計上できます。
経費にできる税金としては、個人事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの税金です。所得税や住民税は必要経費になりません。
デザイナーに例えるとデザイン業は5%の個人事業税かかりますが、事業を運営するために必要な税金と見なせるので、個人事業税は必要経費にできます。またライターに例えると、取材をするために車で移動しているならば、自動車にかかる自動車税も経費にできるでしょう。
控除で節税する
控除とは、所得から一定の金額を差し引く行為のことです。控除には所得控除と税額控除の2種類があります。
所得控除
所得控除には、15種類の控除があります。
配偶者がいると「配偶者控除」、iDeCoで積立をしている人は「小規模企業共済等掛金控除」というように、それぞれの控除に条件が定められています。
主な所得控除は以下のとおりです。
| 控除の種類 | 控除の条件 | 控除額 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 納税者の全てが対象になる控除 | 48万 |
| 配偶者控除 | 控除対象となる配偶者の年収が103万円以下 | 13万~48万 |
| 配偶者特別控除 | 控除対象者の配偶者の年収が103万円以上 | 1万~38万 |
| 扶養控除 | 扶養対象になる扶養親族がいる場合 | 38万~63万 |
| 社会保険料控除 | 社会保険料を支払った場合(国民年金基金も対象) | 全額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済やiDeCoを支払った場合 | 全額 |
| 寄付金控除 | 国や地方公共団体へ寄付した場合(ふるさと納税も含む) | 支出寄付金 ー 2,000円 |
「国民年金基金」や「iDeCo」の掛金の全額が控除の対象になる「社会保険料控除」や「小規模企業共済等掛金控除」は、フリーランスならばぜひとも活用したいところです。
本記事で紹介した他にも適用される所得控除があるので、詳しくは以下の国税庁のホームページを確認してみてください。
参考:所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
税額控除
税額控除は、税額から直接引ける控除のため、所得控除よりも節税効果が高くなる傾向があります。
税額控除には、住宅ローン控除や配当控除などがあります。
| 控除の種類 | 控除の条件 | 控除額 |
|---|---|---|
| 住宅ローン控除 | 住宅ローンを利用している人 | 住宅ローン残高の1% |
| 配当控除 | 企業から剰余金や利益の配当を受け取った人 | 受け取った配当所得の5%~10% |
青色申告特別控除
確定申告には、白色申告と青色申告の2つの申告方法がありますが、青色申告で申告をすると、最大65万円が控除の対象になる「青色申告特別控除」が受けられます。
節税効果が高い控除なので、こちらもフリーランスならばぜひとも活用したい控除です。
まとめ:経費や控除を算出して節税をしよう
本記事ではフリーランスができる節税の方法を解説しました。
フリーランスが節税するには、経費と控除を見直すのが大事です。
今一度、自分の事業で計上できる経費と控除を計算してみましょう。
※2021930修正 所得控除について、一部情報に誤りがございましたので該当部分を削除しました。